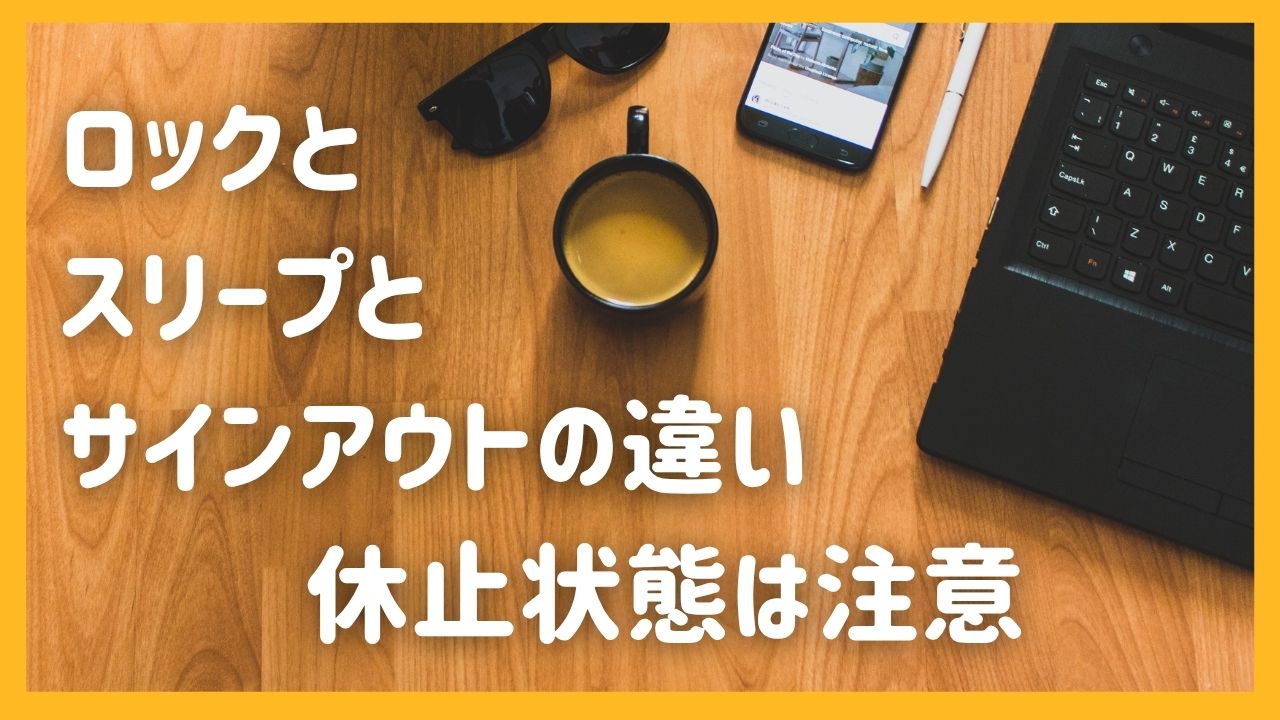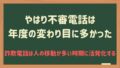パソコンで作業を中断する時に、ロック、スリープ、サインアウト、休止状態などを使います。
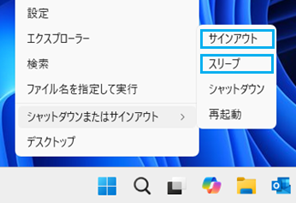
多くてややこしいですね。
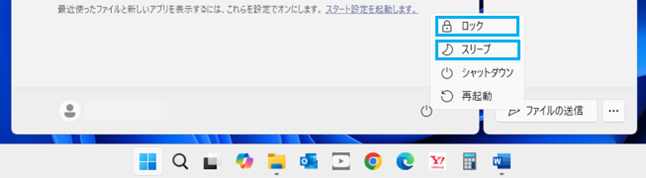
今回は、これらの機能や目的を確認していきます。
ロックとスリープとサインアウト
まず、ロックとスリープとサインアウトの機能や目的を見ていきます。
ロック
機能など
パソコンがパスワードで保護された状態になります。
作業中のアプリはそのまま起動した状態です。
復帰したら、すぐにロック前の状態から始められます。
ロックからの復帰には、パスワードかPINを入力する必要があります。
目的など
セキュリティの確保が目的です。
ロックは、公共の場で作業中に少しだけ席を離れるときに使います。
ロックしたパソコンは他の人には容易には使えなくなります。
スリープ
機能など
電源を入れたままパソコンの動作を一時停止し、パソコンを待機状態(スタンバイ)にします。
スリープから復帰したとき、元の状態が維持されています。
スリープすると、作業中のデータがメモリに保存されます。
ディスプレイやパソコンの一部の電源を切った状態になりますが、作業内容は消えなくて、パソコン本体やメモリの電源はオンのままです。
メリットとして
・電力消費が少ない
・作業への復帰が速い
・ストレージ(HDDやSSD)に負荷がかからない
などがあげられます。
デメリットとして
・電源が絶たれる(停電やコンセント抜け)と作業内容が消える
ことがあげられます。
スリープからの復帰には、パスワードかPINを入力する必要があります。
目的など
省エネと作業への素早い復帰が目的です。
スリープは、プライベートの場で作業中に少し席を離れるときに使います。
サインアウト
機能など
サインインしている状態を解除します。
作業中のアプリは終了した状態になります。
再びサインインするとき、アプリは起動する必要があります。
目的など
個人情報の保護が目的です。
1台のパソコンを共有するユーザーが複数人いて、それぞれアカウントを保有している場合、ユーザーはサインインして使いますが、使い終えたならサインアウトします。
サインアウトは、共有パソコンを使っているユーザーが、席を離れるときに使います。
休止状態
次に、休止状態を見ていきます。
休止状態とは
機能など
パソコンの電源は切った状態です。
次に電源を入れるときに元の状態を復帰させます。
休止状態にすると、作業中のデータがストレージ(HDDやSSD)に保存されます。
後に電源を入れると、作業していたデータはストレージから復元されます。
通常の起動よりは速くパソコンを起動できます。
メリットとして
・スリープよりも電力消費が少ない
・電源が絶たれ(停電やコンセント抜け)ても作業内容の消える可能性は低い
などがあげられます。
デメリットとして
・スリープよりも作業への復帰が遅い
・ストレージに負荷がかかる
などがあげられます。
休止状態からの復帰は、通常の起動と同じくパスワードかPINを入力する必要があります。
目的など
省エネが目的です。
また、データの消失リスクを最小にしつつ作業へ早く復帰するのが目的です。
マイクロソフトサポートに以下の説明があります。
「このオプションは、ノートPCを対象にして設計されたものであり、すべてのPCで使用できない場合があります(InstantGoを備えたPCには休止状態オプションがありません)。休止はスリープよりも電力消費が少なく、PCを再開すると、PCから離れたときの状態に戻ることができます(ただし戻るまでの時間はスリープより長くかかります)。」
「ノートPCやタブレットでは、長時間使用せず、その間バッテリを充電できないとわかっているときは、休止状態にすることをお勧めします。お使いのPCでこのオプションが利用可能かどうかを確認し、利用できる場合はオンにします。」
マイクロソフトサポートはこちら↓
PCをシャットダウン、スリープ、休止状態にする
休止状態は、ノートパソコン向けに設計されたものです。
休止状態は、(ノートパソコンの)作業を一時中断する場面で、内臓バッテリを充電できないときに使います。
休止状態の仕組み
休止状態という言葉はハイバネーション(hibernation)の和訳です。
ハイバネーションはパソコンに備わっている機能で、オペレーティングシステム(OS)の停止モードのひとつです。
ハイバネーションは、PCの電源を切る時にメモリの内容をストレージに保存する機能です。
次に電源を入れると、メモリの内容をストレージから復元します。
つまり、電源を切るとメモリの内容が失われるので、その前にデータをストレージに逃がしているわけです。
こうして、次にパソコンを起動するとき、作業を中断したところから再開できるようにします。
休止状態のSSDへの負荷
ハイバネーションを頻繁に利用すると、内蔵ストレージに負荷がかかります。
ストレージがSSDなら注意が必要です。
SSDの寿命を決めるのは、書き込み回数、空き容量、使用時間、使用環境です。
このうちデータの書き込み回数には上限があり、一般的なSSDの寿命は5~10年といわれます。
ハイバネーションは、大量の書き込みを伴います。
書き込み量が数十GBともなれば、SSDの寿命を縮めます。
そのため、SSD搭載のパソコンは、デフォルトで電源オプションに休止状態が表示されていません。
また、HDD搭載のパソコンでも、電源オプションに休止状態が表示されていないようです。
※最近のPCは休止状態の表示がなくて、筆者が使う4台のPCも表示がない
※設定を変えれば表示はできるが、メーカーが表示させていない意図からすると、変更はお勧めできない
SSDの寿命を伸ばし、パソコンを長く使い続けたいなら、ハイバネーションは使わない方がいいと言えます。
さいごに
ロックとスリープとサインアウトの機能や目的を確認しました。
休止状態については少し踏み込んで仕組みやSSDへの負荷まで確認しました。
補足ですが、スタンバイ(standby)とハイバネーション(hibernation)の言葉の使い方も面倒です。
広義ではこの2つともスリープだからです。
スリープのなかに、スタンバイとハイバネーションがあります。
そして、スタンバイはスリープモードのことであり、ハイバネーションは休止状態のことですから、ややこしさと言葉遣いの難しさはMAXです。
ただ、パソコンの電源メニューが、スリープと休止状態で使い分けているので、その分類で理解すればいいと思います。
ひとつひとつの意味を理解して、違いや注意点を知っていれば役に立つと思います。
この記事が参考になれば幸いです。